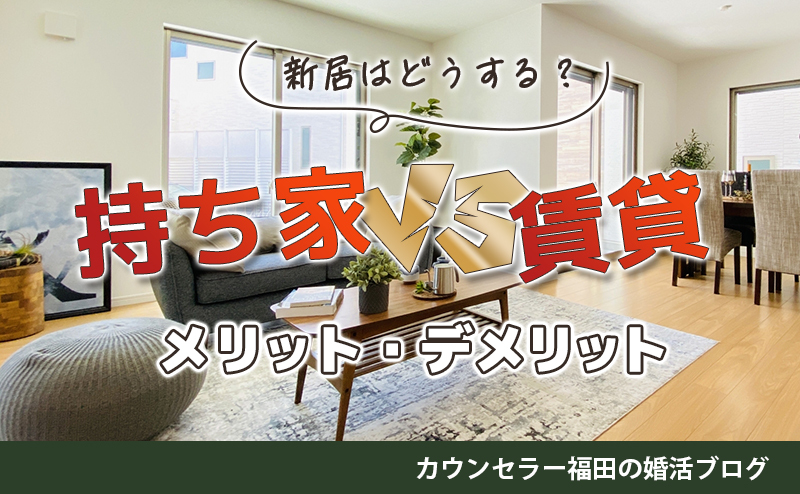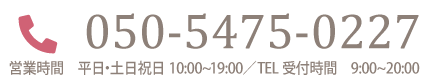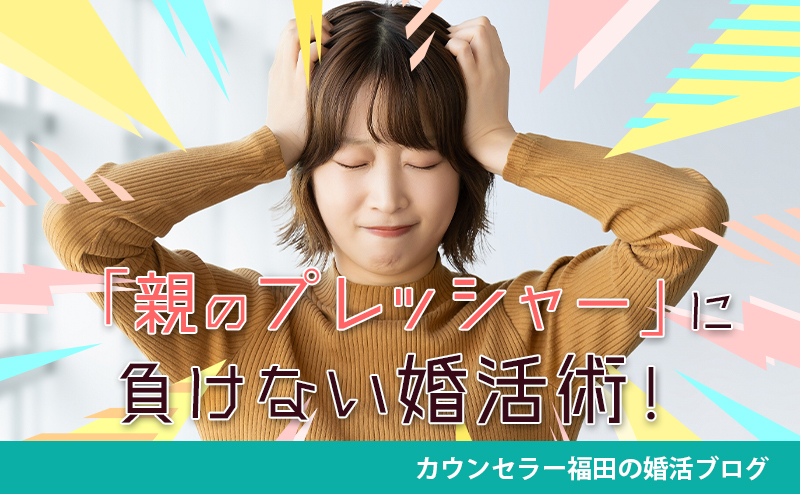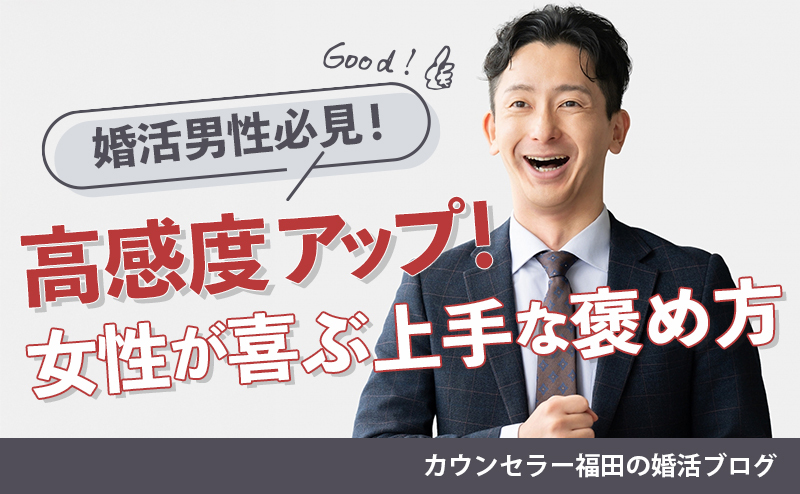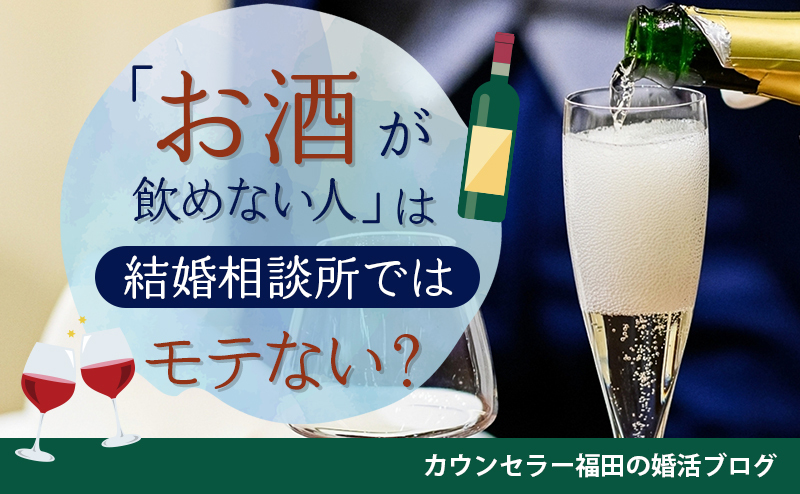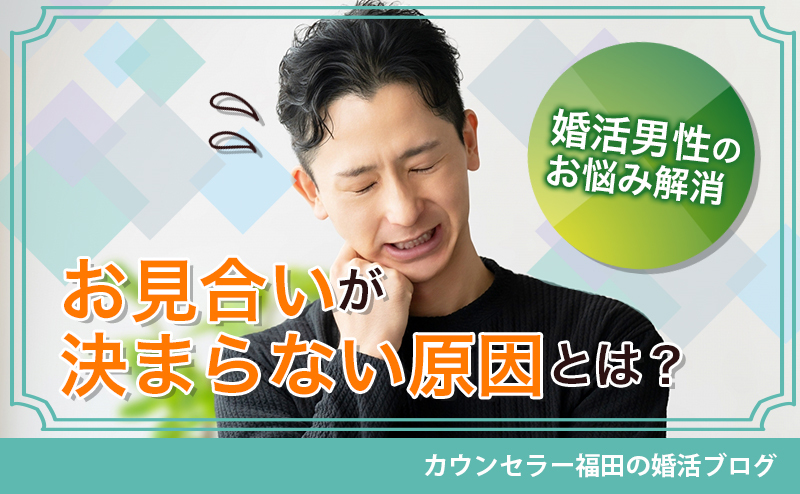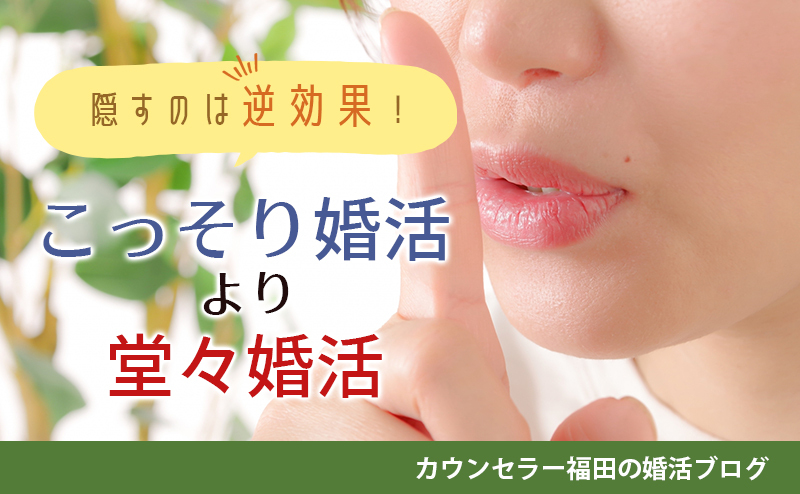結婚相談所でめでたく成婚! 新居はどうする? 持ち家VS賃貸、それぞれのメリット・デメリットを解説!
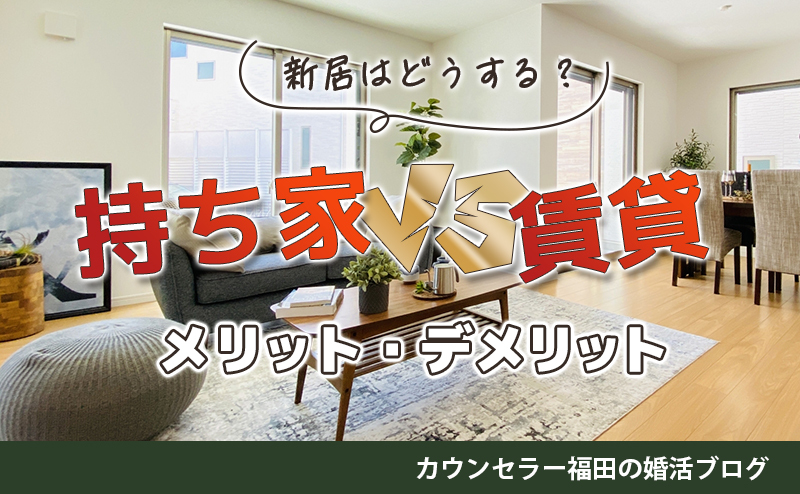
結婚相談所で理想のパートナーと出会い、めでたく成婚!
幸せな生活が始まるその前に、考えておきたいのが「新居」についてです。
新しい生活をスタートするにあたり、「持ち家を購入するか」「それとも賃貸にするか」は大きなテーマです。
どちらにも魅力と注意点があり、一概にどちらが正解というわけではありません。
大切なのは、ふたりのライフスタイルや価値観に合った選択をすること。
この記事では、持ち家・賃貸それぞれのメリット・デメリットをわかりやすくご紹介します。
持ち家のメリット

持ち家には「自分の資産になる」「自由にカスタマイズできる」といった大きな魅力があります。
ローン完済後の安心感や、家族の思い出が積み重なる「人生の拠点」としての価値も見逃せません。
そんな持ち家のメリットをひとつずつ見ていきましょう。
自分の資産になる安心感
住宅ローンを返済すれば、土地と建物は自分たちの資産になります。
老後に住まいをどうするか悩まなくて済むという安心感は大きなポイントと言えるでしょう。
さらに、将来的に売却や賃貸に出すなど、選択肢の幅が広がるのも魅力です。
「家賃を払い続けても自分のものにはならない」という賃貸とは、根本的な違いがあります。
理想の住まいを自由にデザインできる
間取りや内装を自分たち好みにできるのも、持ち家ならではの楽しさです。
壁紙の張り替えや棚の取り付け、ちょっとしたリフォームなど、暮らしに合わせて住まいを育てていけるのが魅力です。
家族構成の変化やライフスタイルの変化にも柔軟に対応できる点は、長く住み続ける上での安心感につながります。
ローン完済後は住居費をぐっと抑えられる
住宅ローンの返済中は出費がかさみますが、完済後は毎月の家賃のような支出が不要になります。
老後にかかる生活費を抑えることができるのは、将来的な大きな安心材料です。
一方、賃貸は年齢を重ねても家賃の支払いが続くため、長期的な家計を考えると、持ち家の方が有利になるケースもあります。
高性能住宅なら快適&省エネ
最近は高気密・高断熱の「高性能住宅」にも注目が集まっています。
冷暖房効率が良く、年間を通じて快適な住環境を維持できるうえに、光熱費の削減にもつながります。
「住み心地」と「家計への優しさ」を両立できる高性能住宅は、これからのマイホーム選びに欠かせないポイントです。
家族の思い出が積み重なる場所になる
何年も同じ家で暮らすことによって、その家は家族の歴史を刻む場所になります。
初めて一緒に暮らした日、子どもの成長を見守ったリビング、毎年ケーキを囲んだダイニング…
そんなひとつひとつの思い出が、家という場所に刻まれていきます。
持ち家は、家族のかけがえのない時間を支える土台となってくれるはずです。
持ち家のデメリット

持ち家には多くの魅力がありますが、現実的なデメリットもいくつかあります。
住宅は人生で最も大きな買い物のひとつですが、それだけに「所有する責任」も伴います。
ここでは、購入前にしっかり理解しておきたい持ち家のデメリットを5つご紹介します。
初期費用や維持費が高額になる
マイホームの購入には、頭金、仲介手数料、登記費用、ローン関連の諸費用など、まとまった初期費用が必要です。
さらに、購入後も固定資産税や火災保険、将来の修繕費など、継続的な支出(ランニングコスト)が発生します。
家を買う前には、「どこまで予算を組めるか」「無理のない返済プランか」をよく見極めることが大切です。
定期的なメンテナンスが必要
家は建てたら終わりではありません。
外壁の塗り直しや屋根の補修、水回り設備の交換など、築年数が経つごとにメンテナンス費用がかかってきます。
数十万円〜100万円単位の出費になることもあるため、計画的に積み立てておくことが安心して暮らすコツです。
毎年かかる税金の負担
持ち家を所有している限り、毎年固定資産税や都市計画税などの支払いが続きます。
ローンを完済した後でも、この税金は一生かかるものです。
物件の評価額や立地によって額も変わるため、事前に確認しておきましょう。
相続でトラブルになるケースも
マイホームは大きな資産であるぶん、相続時に揉めごとの原因になることもあります。
兄弟姉妹がいる場合、「誰が相続する?」「どう分ける?」といった問題が発生するケースも。
こうしたトラブルを避けるためには、生前からの話し合いや遺言書の準備がとても大切です。
住み替えがしにくい
持ち家は大きな決断になるぶん、一度購入すると簡単には引っ越せないというデメリットもあります。
転勤や家族構成の変化など、ライフスタイルが変わっても住まいを柔軟に変えることは難しいことも。
もちろん売却や賃貸に出すという選択肢はありますが、タイミングやエリアによってはすぐに動けない場合もあるため、事前の備えと慎重な判断が必要です。
賃貸のメリット

マイホームに憧れはあっても、「今はまだ持ち家じゃなくていいかも」と感じる方も増えています。
実は、“家を持たない暮らし”にも、現代ならではの合理的なメリットがたくさんあります。
ここでは、賃貸ならではの魅力や強みを、わかりやすくご紹介します。
初期費用がぐっと抑えられる
賃貸住宅では、契約時に敷金・礼金・仲介手数料などが必要ですが、持ち家に比べると初期費用は圧倒的に低く抑えられます。
住宅ローンの頭金や登記費用が不要なため、まとまった資金がなくてもすぐに入居できるのが大きな魅力です。
結婚後のスタートアップ期には、この「身軽さ」が助かるポイントになるかもしれません。
ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる
転勤や転職、出産など、結婚後のライフスタイルは思っている以上に変化していくものです。
賃貸であれば、状況に応じてスムーズに住み替えができるため、家族の変化に合わせた住環境を選びやすくなります。
現代は多様な働き方・暮らし方が当たり前の時代です。
そんな現代にぴったりなのが「賃貸のフットワークの軽さ」です。
固定資産税などの税金がかからない
持ち家では毎年かかる固定資産税や都市計画税などのコストも、賃貸なら一切不要です。
この「見えにくい出費」がないことで、家計に余裕が生まれやすくなります。
長い目で見ると、こうした税金の支払いがないことが賃貸の大きなメリットと感じる方も多いです。
設備のトラブルにも安心対応
給湯器が壊れた、トイレが水漏れした…そんなときも大丈夫。
多くの賃貸物件では、修理や交換は大家さんや管理会社が対応してくれます。
費用の自己負担が少ないのも安心ポイント。
「突然の出費が不安」という方にとって、賃貸のこうしたサポート体制は心強い存在になります。
気軽に住み替えができる自由さ
「通勤しやすい場所に引っ越したい」
「子育てに向いた地域に移りたい」
そんな希望が出てきたときにも、賃貸ならスムーズに住み替えが可能です。
特に都市部では選択肢も多く、その時のライフステージに合った住まい選びがしやすいのも賃貸の大きな魅力です。
住まいに縛られない自由さを重視するなら、賃貸はとても魅力的な選択肢です。
賃貸のデメリット

賃貸には、初期費用の安さや住み替えのしやすさといった魅力がありますが、長い目で見ると注意しておきたいポイントもあります。
「気軽に住める」反面、将来の安心や住まいの自由度では制限があるのが実情。
ここでは、賃貸における代表的なデメリットを4つご紹介します。
自分好みにカスタマイズできない
賃貸住宅では、壁紙の変更やリフォーム、設備の入れ替えに制限があることがほとんどです。
「もっと収納が欲しい」「部屋の雰囲気を変えたい」と思っても、自由に手を加えるのは難しいのが現実です。
原状回復のルールがあるため、自分らしい空間づくりをしたい方にとっては、物足りなさを感じてしまうかもしれません。
家賃を払っても自分の資産にはならない
どれだけ長く住んでも、賃貸住宅は自分の持ち物にはなりません。
家賃は「消えていくお金」であり、最終的に資産として残るものはないため「支払い続けても自分のものにならない」という点に不安を感じる方も多いです。
一方、持ち家であればローンを完済すれば土地と建物が残るため、老後の住まいの安心感にも差が出てきます。
老後もずっと家賃を払い続ける必要がある
年金生活になったあとも、賃貸住宅に住み続ける限り家賃の支払いはずっと続きます。
高齢になるほど収入が限られる中で、毎月の住居費が重くのしかかってくる可能性があります。
持ち家であれば、ローン完済後は支出が大きく減るため、老後の負担を抑える点で有利といえるでしょう。
入居時に制限がかかる場合もある
高齢の方や単身者、小さな子どもがいるご家庭、外国籍の方など、場合によっては「入居を断られる」「希望通りの物件が見つからない」といったトラブルが発生することもあります。
賃貸は「誰でも自由に借りられる」と思いがちですが、年齢・家族構成・国籍などが入居の条件になるケースもあるため、将来的には選択肢が限られる可能性があることも頭に入れておきましょう。
賃貸と持ち家はどちらがお得?

「賃貸と持ち家、どちらが得なんだろう?」
これは結婚後に多くのカップルが直面する悩みのひとつです。
しかし、実際のところ「どちらがお得か」は一概には言えません。
住まいのコストは単純な金額だけでなく、住み方・住む年数・ライフプランによって大きく変わるからです。
長く住む予定なら持ち家が有利なケースも
持ち家の場合、住宅ローンの返済が終われば、その後は大きな住居費がかからなくなります。
しかも土地と建物は自分たちの資産として残るため、老後の安心感にもつながります。
「この先ずっと住む場所を決めている」「将来的には家族で落ち着いた暮らしをしたい」という方には、持ち家の方が経済的メリットが大きくなる可能性が高いです。
数年だけ暮らす予定なら賃貸の方が気軽
一方、転勤の可能性があったり、「ライフスタイルが大きく変わるかもしれない」というご夫婦なら、初期費用や維持費が少ない賃貸の方が、柔軟でコストも抑えやすい選択になります。
住み替えが前提であれば、無理に住宅を購入するよりも、必要なときに必要な場所へ住み替えられる賃貸の方が効率的という見方もできます。
「どちらが得か」より「どう暮らしたいか」で選ぼう
家は、単なる「住む場所」ではなく、これからの暮らしを形づくる大切な舞台です。
損得だけでなく、ふたりの理想の暮らし方・将来の計画・安心感のバランスをしっかり考えて選ぶことが大切です。
「一生住むつもりで家を買いたい」も「しばらくは身軽に過ごしたい」も、どちらも正解です。
大切なのは、自分たちの考えに合った選択をすることです。
賃貸と持ち家の生涯コストを比較

続いて、賃貸と持ち家の生涯コストの違いを比較してみましょう。
今回は、家賃が月10万円の賃貸と、住宅ローンの返済額が月10万円の持ち家を例に考えてみます。
賃貸および持ち家でかかる主なコスト
持ち家の住宅ローンについては、フラット35の金利(2024年7月時点)を参考に、固定金利を1.950%とします。35年の元利均等返済で返済額を月10万円とすると、約3,000万円の借入が可能です。
頭金なし、物件価格3,000万円として試算すると、次のようになります。
| 賃貸 | 持ち家 | |
|---|---|---|
| 初期費用 | 50万円 (家賃5ヵ月分と仮定) | 300万円 (物件価格の10%と仮定) |
| ランニングコスト | 家賃:月10万円 火災保険料:年1万円 更新料:2年ごとに10万円(年5万円) | ローン返済:月10万円 修繕積立金・管理費:月2万円 火災保険料:年1万円 固定資産税・都市計画税:年10万円 修繕費用:20・40年経過時に各200万円 |
経過年数とかかるコストの合計の比較
| 賃貸のコストの累計 | 持ち家のコストの累計 | |
|---|---|---|
| 10年後まで | 1,310万円 | 1,850万円 |
| 20年後まで | 2,570万円 | 3,600万円 |
| 30年後まで | 3,830万円 | 5,150万円 |
| 40年後まで | 5,090万円 | 6,300万円 |
| 50年後まで | 6,350万円 | 6,650万円 |
| 60年後まで | 7,610万円 | 7,000万円 |
上の試算を見ると、30〜40年までは賃貸の方が支出を抑えられていることが分かります。
しかしローン返済が終わると持ち家の住居費はぐっと軽くなり、50年を過ぎる頃には持ち家の方がコストを抑えられる可能性が高くなります。
つまり、「長く住む」ことを前提にするなら、持ち家の方が経済的にお得になることが多いのです。
賃貸か持ち家か、迷ったときの選び方のポイント

ここまでで、賃貸と持ち家それぞれのメリット・デメリットを見てきました。
実際には「どちらがお得か」だけでは決めきれないのが住まい選びの難しいところ。
ここでは、賃貸か持ち家かを選ぶ際に意識したい3つの視点をご紹介します。
転勤や転職の可能性を考えて選ぶ
まずチェックしたいのが、将来の勤務地やライフステージの変化です。
- 転勤が多い職場に勤めている
- 近いうちに転職・移住を考えている
こうした場合は、身軽に引っ越せる賃貸が安心です。
反対に持ち家を選ぶなら、「将来的に売却しやすいか」「貸し出しできるか」といった視点で物件を選んでおくと柔軟に対応しやすくなります。
家族のライフスタイルに合わせて考える
「今の暮らし」だけでなく、これからの家族の変化もイメージして選びましょう。
- 子どもが生まれて家が手狭になるかもしれない
- 親との同居や二世帯を考えている
こうした将来の変化にまだ対応しきれない場合は、まずは賃貸で様子を見てから持ち家を検討するという方法もあります。
一方、ライフスタイルが安定してきたら、自分好みにリフォームやDIYできる持ち家を選ぶのも◎。
「こんな暮らしがしたい!」というイメージがある方は、持ち家の方が満足度が高くなりやすいです。
老後の生活設計も視野に入れておく
働いているうちは毎月の家賃やローン返済に困ることは少ないかもしれません。
しかし、将来的に収入が年金のみになると、家賃を払い続けるのは負担になる可能性も大いにあります。
「老後は住居費の負担を減らしたい」と考えるなら、ローン完済のタイミングを逆算して早めに持ち家を購入しておくのが安心です。
もちろん、貯金や年金で十分に家賃をカバーできる見込みがある場合は、賃貸を選ぶのもひとつの選択肢となるでしょう。
重要なのは、自分たちのライフプランに合った形で「無理のない住まい」を選ぶことです。
自分たちに合った住まい選びを
住まいを選ぶときには、単なる「お金の損得」だけでなく、以下のような視点も大切です。
- ライフスタイルの変化への対応力
- 将来の収入・支出の見通し
- どんな暮らしをしたいかという価値観
賃貸にも持ち家にも、それぞれに魅力があります。
自分たちに合った選択をすることで、より安心で心地よい結婚生活をスタートできるはずです。
香川県・愛媛県・徳島県・高知県で婚活するなら結婚相談所ハッピーブライダルへ!

今回の記事はいかがだったでしょうか。
持ち家と賃貸それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが正解とは一概には言えません。
重要なのは「どんな暮らしがしたいか」「将来どうありたいか」というふたりの価値観やライフプランに合った住まいを選ぶことです。
- 長く落ち着いて暮らしたい → 持ち家が安心
- ライフスタイルの変化に合わせたい → 賃貸が柔軟
といったように、今と未来の両方を見据えて選ぶことが大切です。
また、家の購入や引っ越しは人生の大きな節目でもありますが、その前に何よりも大切なのは「生涯を共にするパートナーと出会うこと」ではないでしょうか?
住まいの話は、ふたりで将来を描ける関係があってこそ。
だからこそ、まずは信頼できるパートナーとの出会いから始めてみませんか?
結婚相談所ハッピーブライダルでは、会員様一人一人に担当の婚活カウンセラーがきめ細やかなサポートを行っているため安心して活動いただけます。
自分だけで婚活を進める自信がない人や、初めて婚活するという人も、すぐに相談をして解決していくことができ、婚活の不安や難しさを軽減できます。
また、結婚相談所ハッピーブライダルがどんな結婚相談所か事前に知っていただくために、正式入会前に試していただける「お試し会員コース」もあり、自分にあった相談所かどうかを事前に確認できるので安心です。気になる方はぜひ一度ご相談ください。

結婚相談所ハッピーブライダルは全国大手とよばれる複数の主要連盟に加盟しており、複数の主要連盟サービスに登録されている会員データが利用できるため出会いの可能性が広がります。
また、16軒の結婚相談所が加盟している四国エリア最大級の結婚相談所連盟KMA(一般社団法人かがわ結婚推進協会)にも加盟しており、四国4県や岡山などに独自の会員様も多数在籍し、会員制の婚活パーティーも開催しておりシステム非掲載の会員様もご紹介することが可能です。
結婚相談所ハッピーブライダルは29年以上の運営実績があり、香川県を中心に愛媛県・岡山県・徳島県・高知県などの隣接県とのご縁も橋渡しする地域密着型の結婚相談所です。お相手選びから交際・婚約・結婚に至るまでフルサポートします。
また、担当の婚活カウンセラーへの連絡もメールや電話は当たり前、LINEでレスポンスよく連絡も取れます。
どんな時でも、些細な相談事でも、いつでも気兼ねなくご連絡ください。
結婚相談所を利用しているものの、素敵なお相手となかなか出会えず、うまくいっていないという方や、現在の結婚相談所との掛け持ち、乗り換えをお考えの方のご相談やサポートにも対応させていただいております。
知識と経験豊富なスタッフが誠心誠意サポートしますので、まずは一度、お気軽にご相談ください。
\ まずは最初の1歩を踏み出しましょう /
今すぐ試そう!無料紹介体験
実際のコーディネーターと話してみる
婚活がオンラインでも可能!